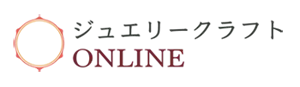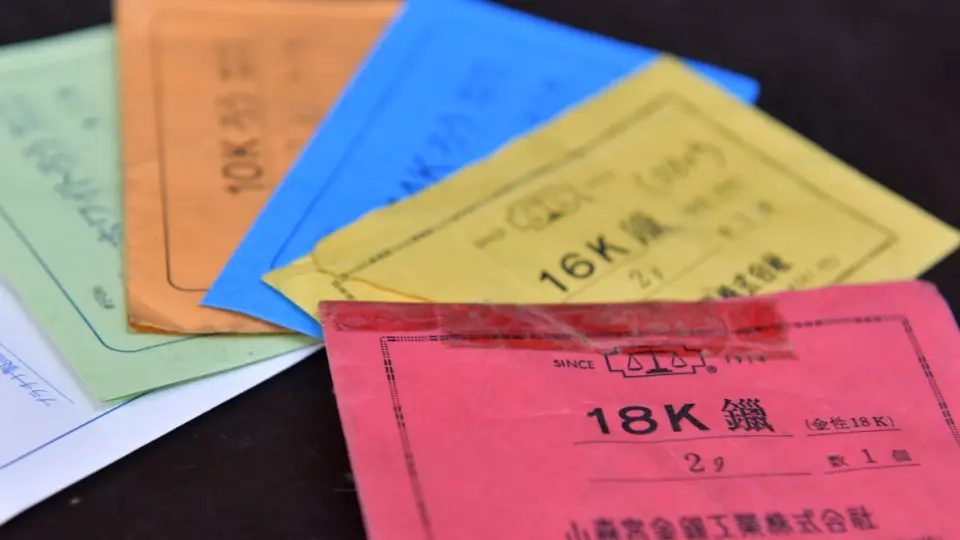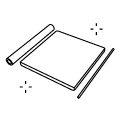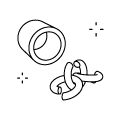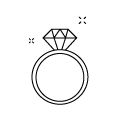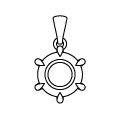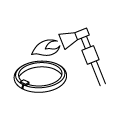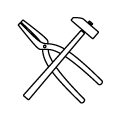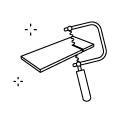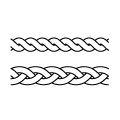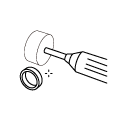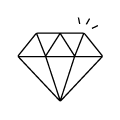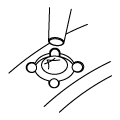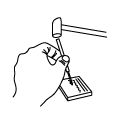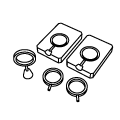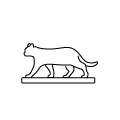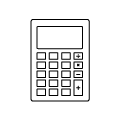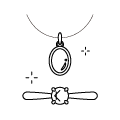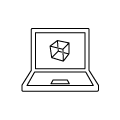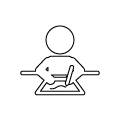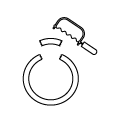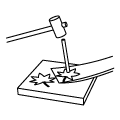私は、もともと本業である「ジュエリー製作」とは別に、外部からの依頼を受けて、ホームページを作ってみたり、チラシを作ってみたり、カメラマンのような真似事をしてみたりと、けっこういろいろやってきました。
正直に隠さずに話すと
「お金」のためにやった
という事になりますが、人から何か仕事を頼まれると、
けっこう、断れない
という方も多いのではないでしょうか。
でも、そのような仕事は、一過性のものであって、自分が目指す目標やビジョンに合わず、
結局、中途半端に終わってしまった
という事が多くあります。
今回は、私の経験も踏まえて
「選択と集中」
について、私なりの法則をお話ししたいと思います。
この法則を頭にいれておけば、
どんな話がきても迷うことなく判断できます。
あれこれ手をつけてしまい、
どこに向かえばいいかわからない
と言う方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。